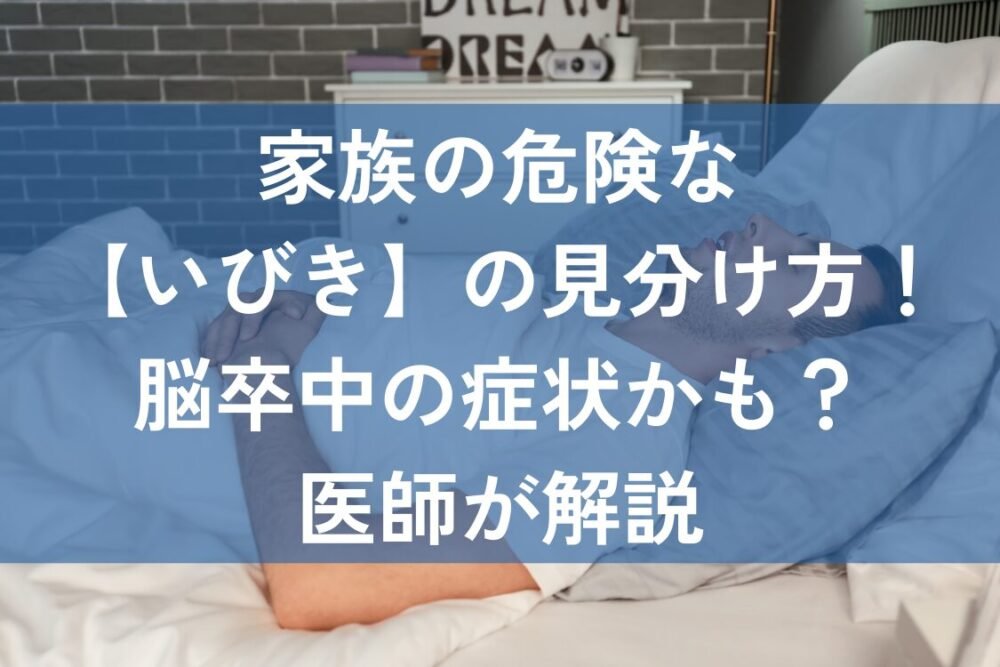家族のいびき、ただの騒音だと思ってはいませんか?
実は、そのいびきが命に関わる病気のサインかもしれません。
2019年の厚生労働省の調査によると、脳卒中による死亡者数は年間約10万人で、これは日本人の死因の第4位に相当します。 もしかしたら、身近な人の危険な「いびき」が、脳梗塞や脳出血などの脳卒中を発症する前兆である可能性も。
この記事では、いびきの種類、脳卒中との関連性、そして緊急時の対処法まで、医師が詳しく解説します。
ご家族の健康を守るためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
危険ないびきの種類と見分け方4選
ご家族のいびき、気になりますよね。もしかしたら、深刻な病気のサインかもしれません。
ここでは、危険ないびきの種類と見分け方を4つ、解説します。
「ただのいびき」と安易に考えて放置せず、種類と見分け方を知って、ご家族の健康を守りましょう。

単純いびき:特徴と見分け方
単純いびきは、空気の通り道(気道)が狭くなることで、のどの奥の粘膜が振動して音が鳴る現象です。
例えば、仰向けで寝ていると、舌が喉の奥に落ち込み気道を狭くしてしまうことがあります。これがいびきの原因となるのです。
単純いびきには、大きく分けて2つの種類があります。
- 散発性いびき: 普段はいびきをかかない方が、疲労や飲酒、風邪などによって一時的にいびきをかく状態です。
- 習慣性いびき: 常に気道が狭いため、毎日のようにいびきをかきます。
散発性いびきは、原因となっているものを取り除けば自然と改善します。一方、習慣性いびきは、毎日いびきをかきますが、呼吸が止まったり酸素が不足する状態ではありません。
ただし、習慣性いびきは将来的に、より深刻ないびきへと進行する可能性もあるため、注意が必要です。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群:危険な無呼吸のサイン
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、寝ている間に呼吸が繰り返し止まる病気です。
のどが塞がって空気が通らなくなり、10秒以上続く無呼吸状態が1時間に5回以上繰り返されます。大きないびきをかいた後、急に静かになり、また大きないびきをかく、という症状を繰り返すのが特徴です。
日中の強い眠気や倦怠感、集中力の低下といった症状が現れます。また、SASは高血圧や心臓病、脳卒中のリスクを高めるため、放置せずに適切な治療を受けることが重要です。
治療には、マウスピースを使用する方法や、CPAP(シーパップ)という装置を使って鼻から空気を送り込む方法などがあります。CPAPとは、Continuous Positive Airway Pressure の略で、日本語では「経鼻的持続陽圧呼吸療法」と言います。
中枢性睡眠時無呼吸症候群:神経疾患の可能性
中枢性睡眠時無呼吸症候群は、脳の呼吸中枢の異常が原因で起こります。呼吸をコントロールする脳からの指令がうまく伝わらず、呼吸が不安定になります。閉塞性睡眠時無呼吸症候群とは異なり、のどが塞がっているわけではありません。
いびきは必ずしも起こるとは限らず、無呼吸の程度もさまざまです。神経疾患が原因で起こる場合もあるため、詳しい検査が必要です。
中枢性睡眠時無呼吸症候群は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群に比べて稀な病気です。
上気道抵抗症候群:無呼吸を伴わない呼吸努力
上気道抵抗症候群(UARS)は、空気の通り道である上気道が狭くなっている状態です。単純いびきよりも呼吸が苦しく、息苦しさで目が覚めることもあります。
睡眠時無呼吸症候群の軽症と考えられており、無呼吸はみられませんが、昼間の眠気などの症状が現れることがあります。UARSは、単純いびきと閉塞性睡眠時無呼吸症候群の中間に位置するような病気と言えるでしょう。

家族の気づきの重要性
あるとき、脳ドックで偶然見つかった未破裂脳動脈瘤の手術後、患者さんの夫から「妻のいびきがひどいので検査してほしい」と相談がありました。検査の結果、かなり重度の睡眠時無呼吸があることがわかり、治療を開始しました。
実はこの動脈瘤と睡眠時無呼吸には関連があり、いびきを放置していたら動脈瘤が破裂する危険もありました。
家族の何気ない一言が命を救うこともあるのです。いびきを「単なる音」と思わず、大切な健康シグナルとして捉えることが重要です。
いびきが疑われる脳卒中の症状と対処法

いびきは、誰にでも起こりうる症状ですが、実は重大な病気のサインである可能性があります。
特に、脳卒中との関連が指摘されており、決して軽視できるものではありません。
今回は、いびきと脳卒中の関係性について、そして緊急時の対処法を詳しく解説します。
脳卒中の初期症状:顔の麻痺、ろれつが回らない、手足の痺れ
脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳の細胞が酸素や栄養を受け取れなくなり、脳に障害が起こる病気です。一刻を争う病気であり、後遺症が残る可能性もあるため、迅速な対応が非常に重要です。
脳卒中の初期症状は様々ですが、代表的なものとして以下の3つが挙げられます。
- 顔の麻痺:顔が歪んだり、片方の口角が下がったり、笑顔がうまく作れなくなったりします。鏡を見て左右非対称になっていることに気付くこともあります。
- ろれつが回らない:言葉が不明瞭になったり、呂律が回らなくなったり、舌がもつれたりする、といった症状が現れます。
- 手足の痺れ:片方の手足がしびれたり、力が入らなくなったり、感覚が鈍くなったりします。麻痺と同様に、左右差がある場合に特に注意が必要です。
これらの症状に加えて、激しい頭痛、急な激しいめまい、嘔吐なども見られることがあります。
これらの症状が単独、あるいは複数同時に現れた場合は、脳卒中の可能性を疑い、すぐに医療機関を受診することが大切です。
いびきと脳卒中の関係性:睡眠時無呼吸症候群のリスク
いびき自体は病気ではありませんが、睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)の症状の1つである場合があります。睡眠時無呼吸症候群とは、寝ている間に呼吸が何度も止まる病気です。
この病気は、高血圧や心臓病のリスクを高めるだけでなく、脳卒中のリスクも高めることが知られています。
▶【脳卒中になりやすい人】共通点はこれだった!特徴を知ってリスク回避|医師が徹底解説
睡眠時無呼吸症候群は、特に男性において脳卒中のリスクを約2倍に高めるとの報告もあります。
大きないびきをかき、日中に強い眠気や倦怠感、集中力の低下といった症状がある場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。医療機関を受診し、検査を受けることをおすすめします。
睡眠時無呼吸症候群の検査では、睡眠中の呼吸状態や血液中の酸素飽和度を調べます。
緊急時の対応:救急車を呼ぶ際の注意点
いびきをかいている人が急に反応しなくなり、呼びかけても揺すっても反応がない場合は、脳卒中の可能性があります。このような場合は、直ちに救急車を呼ぶことが重要です。
救急車を呼ぶ際には、落ち着いて、以下の情報を伝えられるようにしましょう。
- 患者の年齢と性別
- 現在の症状(いびき、意識がない、など)
- いつから症状が現れたか
- 既往歴(過去にかかった病気)や服用中の薬
救急隊員が到着するまで、患者さんの安全を確保し、可能であれば呼吸や脈拍を確認しましょう。
脳卒中の予防:生活習慣改善のポイント
脳卒中は、生活習慣の改善によって予防することができます。
特に、肥満は気道を圧迫し、いびきや睡眠時無呼吸症候群を悪化させるだけでなく、脳卒中のリスクを高める要因となります。適正な体重を維持するために、バランスの良い食事と適度な運動を心がけましょう。
喫煙は血管を傷つけ、脳卒中のリスクを高めます。禁煙を強くおすすめします。
また、過度な飲酒も脳卒中のリスクを高める可能性がありますので、お酒は適量を心がけましょう。
高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は脳卒中の危険因子です。適切な治療と管理を行うことで、脳卒中のリスクを軽減することができます。
専門医への相談:脳神経外科、神経内科、呼吸器内科
いびきや睡眠時無呼吸症候群が気になる場合は、脳神経外科、神経内科、呼吸器内科などの専門医に相談しましょう。検査によって睡眠中の呼吸状態や酸素飽和度を調べ、適切な診断と治療を受けることができます。
ご自身のいびきを軽く考えず、専門医への相談も検討してみてください。早期発見、早期治療によって、健康な生活を守りましょう。
まとめ

いびきと一口に言っても、種類があり、深刻な病気のサインである可能性があります。
特に、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、脳卒中や心筋梗塞のリスクを高めるため注意が必要です。大きないびきをかいた後に呼吸が止まる、日中の強い眠気や倦怠感がある場合は、SASの可能性も考え、早めに医療機関を受診しましょう。
日頃から、バランスの良い食事や適度な運動、禁煙など、生活習慣の改善を心がけることも大切です。
ご自身のいびきを軽く考えず、少しでも気になることがあれば、専門医に相談し、健康な毎日を送りましょう。
参考文献
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnt/36/3/36_254/_pdf/-char/ja
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnt/39/4/39_554/_pdf/-char/ja
- https://www.m3.com/clinical/open/journal/28204

-情報提供医師
松本 美衣 Mie Matsumoto
和歌山県立医科大学 医学部卒業
戻る